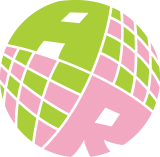TOEIC満点への道 Vol.12
継続できる人は必ず伸びる – 企業研修で見た成功パターン
はじめに
前回の記事では、TOEIC 880点到達までの学習ルーティンについてご紹介しました。今回は、企業出張TOEIC講座の講師として2年目を迎えた私が、現場で目の当たりにした「継続できる人」と「挫折する人」の決定的な違いについてお伝えします。
この経験は、私自身の学習観を大きく変えることとなりました。
講師2年目:週3〜4回の企業出張授業
2014年、企業出張TOEIC講座は2年目を迎えました。週3〜4回、工業団地にある大手企業の工場へ通う日々。初級者クラス(目標470点)と上級者クラス(目標650点)を合わせて、30〜40名の受講者を担当していました。
講師1年目は、正直に言って自分のことで精一杯でした。「どう教えればいいのか」「自分の英語力で大丈夫か」という不安ばかり。しかし2年目になると、余裕が生まれ、受講者一人ひとりの様子をじっくり観察できるようになりました。
そこで気づいたことがあります。
「伸びる人」と「伸びない人」の差は、才能や初期スコアではなく、「継続」にあるという点です。
半年間で見えた「くっきりとした差」
企業研修は約6ヶ月間のプログラムでした。最初と最後にTOEICの模擬テストを実施し、スコアの伸びを測定します。
半年後、結果は驚くほどはっきりと分かれました。
伸びた人の特徴
-
初級者クラス(目標470点): 300点台から450〜500点へ(150〜200点アップ)
-
上級者クラス(目標650点): 500点台から600〜700点へ(100〜150点アップ)
一方で、伸び悩んだ人もいました。
伸びなかった人の特徴
-
スコアが10~30点程度しか上がらない(誤差の範囲)
-
むしろ下がってしまう人さえいた
この「差」は何だったのか。初期スコアや年齢、学歴ではありませんでした。決定的な違いは、「継続できたかどうか」だったのです。
工場で見た「継続の工夫」- 休憩時間の単語帳
特に印象的だったのは、上級者クラスのある受講者です。30代後半の男性で、製造ラインのリーダー的存在。彼は毎回、授業が始まる前に必ず単語帳を開いていました。
「先生、これ、今日覚えたやつです」
休憩時間、昼食後、通勤の電車の中。彼は常にポケットサイズの単語帳を持ち歩き、5分、10分の細切れの時間を徹底的に活用していました。
同僚と問題を出し合う「楽しさ」
さらに驚いたのは、彼らが同じ職場の仲間たちと、休憩時間に英語の問題を出し合っていたことです。
「今日のPart 5、全然わからなかったよな」
「あれ、答えは何だった?」
「確か、前置詞がポイントだったと思う」
こうしたやり取りが、工場の休憩室で自然に起こっていたのです。彼らにとって、TOEICは「苦行」ではなく、仲間と共有できる「共通の話題」になっていました。
この雰囲気を作り出せた職場は、全体的にスコアの伸びが顕著でした。
伸びる人の共通点①:「短時間でも毎日触れる」
企業研修で観察した結果、伸びる人には明確な共通点がありました。
重要なのは「量」ではなく「頻度」です。
「1日30分でも毎日続ける」人が勝つ
伸びなかった人の典型的なパターンは、こうでした。
-
「今週は忙しくて全然できなかった」
-
「週末にまとめて3時間やろうと思ってます」
-
「来週からまた頑張ります」
一方、伸びた人は違いました。
-
「昨日は10分しかできませんでしたが、単語だけは見ました」
-
「通勤電車で毎日リスニング聞いてます」
-
「寝る前に5問だけ解くようにしてます」
週末に3時間勉強するより、毎日10分続ける方が、圧倒的に効果がありました。
伸びる人の共通点②:「完璧主義」を捨てている
もう一つの共通点は、完璧を求めていないことでした。
この姿勢こそが、継続を可能にする秘訣です。
「わからなくても、とりあえず進む」
伸びなかった人は、こんな言葉をよく口にしました。
-
「この文法が完全に理解できるまで、次に進めない」
-
「全部の単語を覚えてから問題を解きたい」
-
「ちゃんと勉強する時間が取れるまで、手をつけたくない」
一方、伸びた人はこう言いました。
-
「わからないところは飛ばして、とりあえず最後までやりました」
-
「単語は8割くらい覚えたら、次の章に進んでます」
-
「完璧じゃないけど、毎日ちょっとずつやってます」
「60点でもいいから、毎日進む」。この姿勢が、継続を可能にしていました。
伸びる人の共通点③:「楽しさ」を見つけている
最も重要だと感じたのは、「学習に楽しさを見つけている」ことです。
義務ではなく、ゲーム感覚で
工場の休憩室で問題を出し合っていた受講者たちは、まるでクイズ番組を楽しむように英語を学んでいました。
-
「今日のPart 7、時間内に解けた!」
-
「前回間違えた問題、今回は正解した!」
-
「先週より10個多く単語覚えた!」
こうした小さな成功体験の積み重ねが、継続のエネルギーになっていました。
一方、伸びなかった人は、英語を「義務」「苦行」と捉えていました。この意識の差が、半年後の結果に如実に現れました。
挫折する人の典型的なパターン
逆に、途中で挫折してしまった人には、こんな特徴がありました。
パターン①:「忙しい」を理由にする
-
「今週は残業が多くて…」
-
「家族の用事があって…」
-
「体調が悪くて…」
もちろん、本当に忙しいのは事実です。しかし、伸びた人も同じように忙しかったのです。違いは、「忙しくても5分だけやる」という選択をしたかどうかでした。
パターン②:「結果」ばかりを求める
-
「3ヶ月勉強したのに、まだ100点しか上がらない」
-
「こんなに頑張ってるのに、全然できるようにならない」
こうした言葉を口にする人は、短期間での劇的な変化を期待していました。しかし、英語力の向上は緩やかな坂道です。急な階段ではありません。
毎日の小さな積み重ねが、半年後、1年後に大きな差となって現れる。それを信じられなかった人は、途中で諦めてしまいました。
パターン③:「他人と比較」してしまう
-
「あいつはもう600点取ってるのに、自分はまだ500点だ」
-
「同期の中で自分だけスコアが低い」
他人と比較することで、モチベーションが下がってしまう人もいました。しかし、大切なのは「過去の自分」と比較することです。
3ヶ月前の自分より、今の自分は成長している。それだけで十分なはずなのに、他人の目を気にしすぎて、自分の成長を認められない。これは非常にもったいないことでした。
モチベーションに頼らない「仕組み」の重要性
企業研修で学んだ最大の教訓は、「モチベーションに頼るな」ということでした。
やる気は必ず下がる
最初は誰でもやる気に満ちています。しかし、2週間、1ヶ月と経つうちに、必ずモチベーションは下がります。これは避けられない事実です。
伸びた人は、モチベーションに頼らない「仕組み」を作っていました。
-
毎朝7時に必ず単語帳を開く(習慣化)
-
通勤電車では必ずリスニング音源を聞く(環境設計)
-
同僚と毎週金曜日に進捗を報告し合う(仲間の力)
こうした「仕組み」があれば、やる気がなくても、自動的に学習が続きます。
自分自身の経験との共通点
企業研修で受講者を見ながら、私は自分自身の過去を重ねていました。
ニュージーランドから帰国後、図書館に毎日12時間通い続けた自分。あれも、モチベーションではなく、「図書館に行く」という習慣があったから続けられたのだと、改めて気づきました。
「やる気が出たらやる」ではなく、「やる気がなくてもやる」。
この姿勢こそが、継続の秘訣でした。
継続できた人が手にしたもの
半年間の研修を終えた受講者たちは、スコアアップ以上のものを手にしていました。
-
自信:「自分でもやればできるんだ」という自己肯定感。これは、英語学習だけでなく、仕事や人生の他の場面でも活きる力です。
-
習慣:毎日コツコツ積み重ねる力。これは一生使えるスキルです。
-
仲間:同じ目標に向かって努力する仲間。工場の休憩室で問題を出し合っていた彼らは、研修が終わった後も、互いに刺激し合う関係を築いていました。
【振り返って思うこと】
企業出張TOEIC講座の2年目、私は講師として、そして一人の学習者として、大きな学びを得ました。
「継続できる人は、必ず伸びる。」
才能や初期スコアは関係ありません。毎日少しずつでも続けられるかどうか。それが全てでした。
そして、この教訓は、自分自身のTOEIC学習にも活かされることになります。
【次回予告】
次回は、「リスニング満点への道 – 495点を安定させる方法」をお届けします。
2014年5月、私はついにTOEICリスニングで495点満点を達成しました。South Park効果がついに花開いた瞬間です。どのような練習法で満点に到達したのか、具体的な方法をお伝えします。
【今回のポイント】
-
伸びる人と伸びない人の差は「才能」ではなく「継続」
-
1日30分より、毎日5分の方が効果的
-
完璧主義を捨て、60点でも毎日進む
-
モチベーションに頼らず、「仕組み」を作る
-
小さな成功体験の積み重ねが、継続のエネルギー
【プロフィール】
-
亀井勇樹(42歳)
-
栃木県宇都宮市「アカデミック・ロード」英語塾講師
-
保有資格:TOEIC L&R 990点、英検1級、通訳案内士(英語)